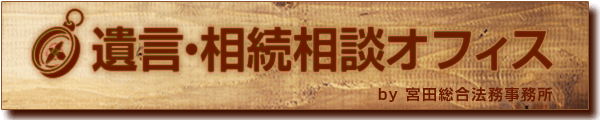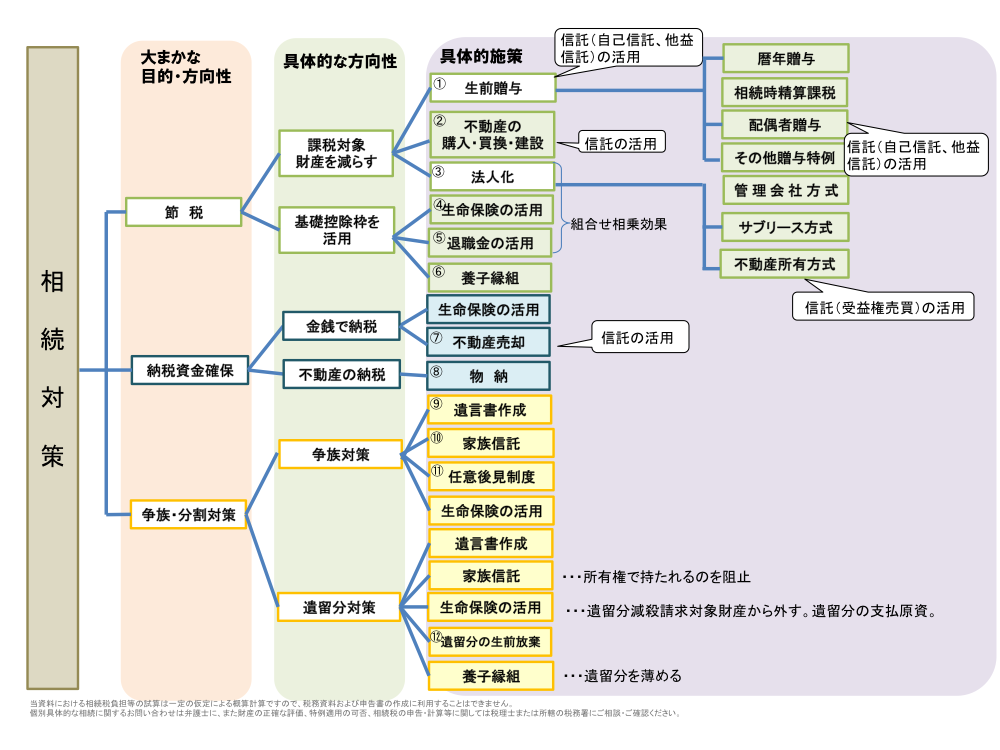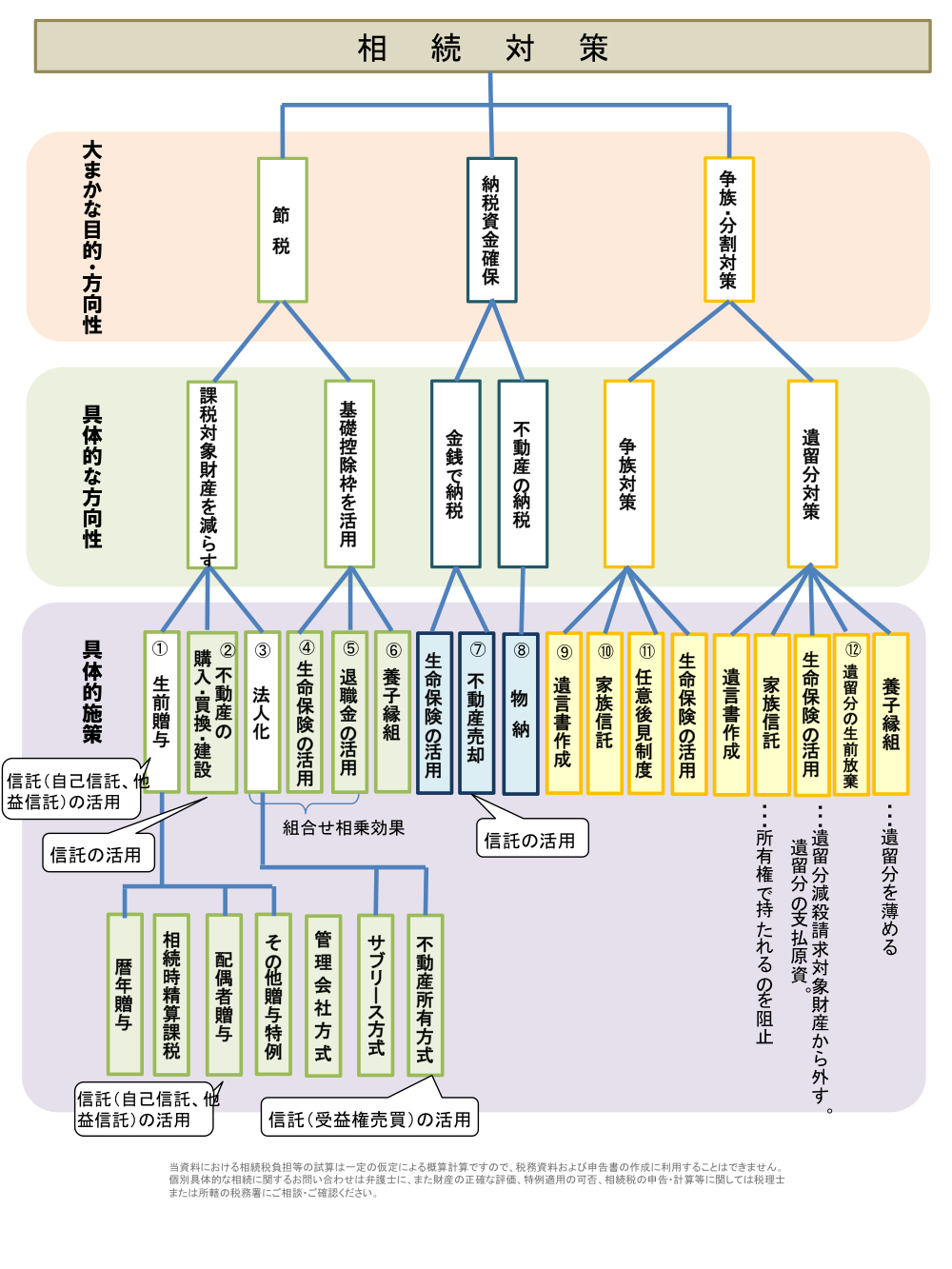死亡退職金の非課税枠の活用
被相続人に支給されるべきであった退職手当金(※1)や功労金等を、被相続人が死亡したことにより、その相続人等が「死亡退職金」として受け取った場合、本来の法律上の遺産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります(相続人以外の人が受け取った場合でも相続税の課税対象となります)。
ただし、死亡退職金には、相続人の生活保障等を考慮し、生命保険と同様、≪ 金500万円 × 法定相続人の数 ≫(※2)の非課税枠が設けられています。この非課税限度額を利用することで、会社経営者(役員)が死亡しても、遺される相続人や事業後継者が相続税の納税資金や生活費を確保しやすくなります。
会社は、法人契約で、経営者(=被相続人)を被保険者にした生命保険に加入することができます(契約者兼受取人が会社)。経営者の死亡により会社に生命保険金が支払われますが、これを会社で定める「退職金規程」に従って経営者の相続人にそのまま全額支払うことで、実質会社への課税が無いばかりでなく、死亡退職金の非課税限度の枠内であれば、所得税も相続税もかからず全額相続人に共済金を渡すことが可能となります。
(※1)退職手当金等とは退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものをいいます。
(※2)法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして扱います。また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
小規模企業共済で個人事業主でも死亡退職金を
個人事業者は、原則として「退職金」というが概念がありません。しかし、国の制度である「小規模企業共済」という制度を活用すれば、個人事業主でも退職金をつくることができます。
この制度は、月額金1,000円~金70,000円までの掛金が全額損金(所得から経費として控除される)となり、将来支払われる共済金は、税法上「退職所得」(一時金として一括で受け取るの場合)または「公的年金等の雑所得」(分割払いで受け取る場合)扱いになります。
また、共済契約者(被相続人)が死亡した場合、法定相続人は共済金を死亡退職金として受け取ることができますので、前述の死亡退職金の非課税枠を使うことができます。つまり、小規模企業共済を死亡退職金の積立として活用することにより、死亡退職金の非課税限度の枠内であれば、個人事業主でも、所得税も相続税もかからずに相続人に共済金という財産を残すことが可能となります。
なお、法人の死亡退職金も、小規模企業共済における死亡退職金も、「遺産」ではありませんので、遺産分割協議の対象外となります。つまり、会社の退職金規程や小規模企業共済において定められた共済金受給権順位に基づく受取人に支払われます。
【図】 小規模企業共済井における共済金受給権順位表
| 受給権順位 | 共済契約者との関係 | |
| 第1順位者 | 配偶者 | 戸籍上の届出はしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった方を含む(※1) |
| 第2順位者 | 子 | 共済契約者が亡くなった当時、主としてその収入によって生計を維持していた方(※2) |
| 第3順位者 | 父母 | |
| 第4順位者 | 孫 | |
| 第5順位者 | 祖父母 | |
| 第6順位者 | 兄弟姉妹 | |
| 第7順位者 | その他親族 | |
| 第8順位者 | 子 | 共済契約者が亡くなった当時、その収入によって生計を維持していなかった方(※2) |
| 第9順位者 | 父母 | |
| 第10順位者 | 孫 | |
| 第11順位者 | 祖父母 | |
| 第12順位者 | 兄弟姉妹 | |
| 第13順位者 | 曾孫 | |
| 第14順位者 | 甥・姪 | |
※1 内縁関係の配偶者も受け取ることができますが、その場合、事実上婚姻関係と同様の事情にあったことの証明願等内縁関係を証する書類の提出が求められます。
※2 「生計を維持していた」とは、共済契約者の収入で生活費・療養費等の大部分が援助され、確定申告において扶養親族として申告している場合をいいます。