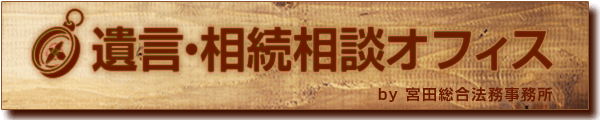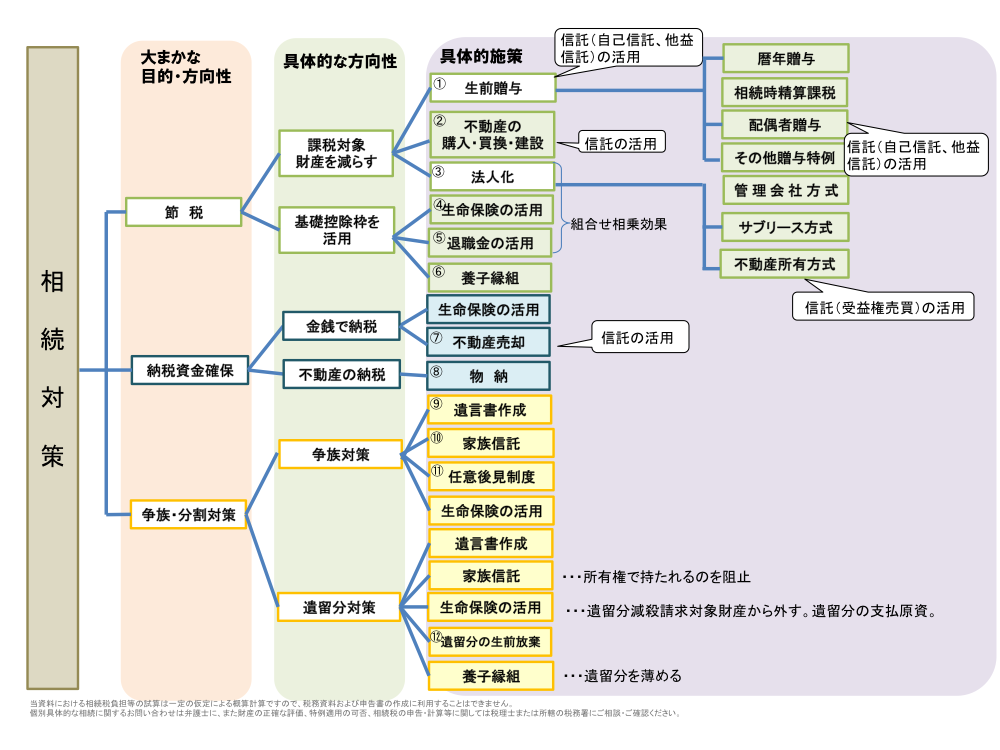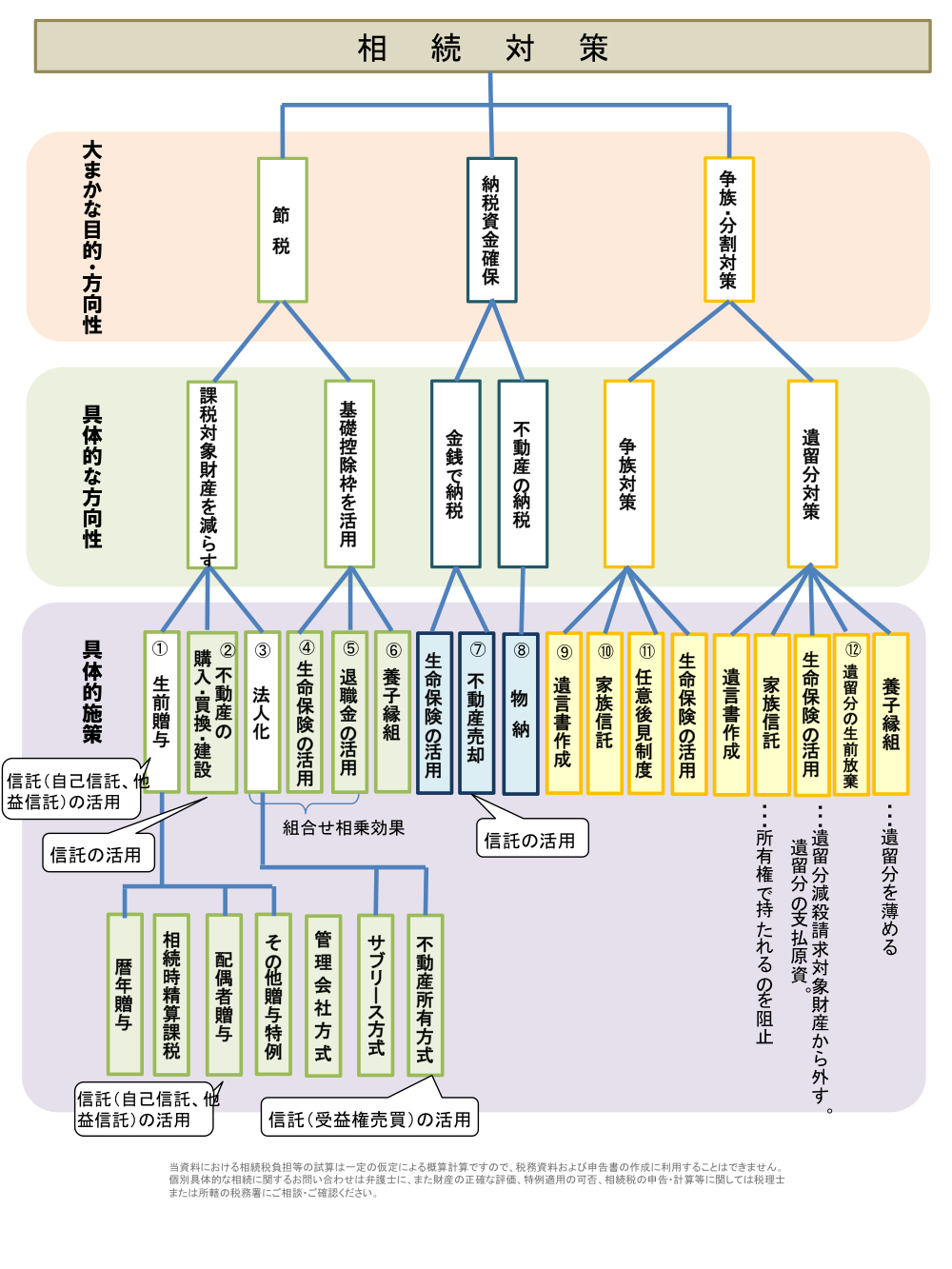目次
1.遺留分とは
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、“被相続人の死亡によりその相続人が受け取れるものとして民法上最低限保証された遺産の取り分”を言います。
被相続人は、自己の財産を自由に処分できるため、例えば「法定相続人以外の者に全財産を遺贈する」旨の遺言書を作ることができます。
この場合、相続人は、遺言がなければ自分が遺産を受け取れたのに、遺言があることにより全く遺産を受け取れなくなるという結果になります。法定相続人は、自分が遺産を受け取れるだろうと期待するものですし、被相続人の死亡によって、場合によっては遺された家族が住む家を失うという状況に追い込まれてしまうのは、好ましくありません。
そこで、遺される法定相続人の生活の安定の観点から、民法は兄弟姉妹を除く相続人(配偶者、子供等の直系卑属、父母等の直系尊属)に、遺産の最低限の取り分として遺産の一定割合の取得を保証しているのです。
これが「遺留分」という制度です。
2.遺留分のある相続人(遺留分権利者)とは
遺留分の権利を主張できる相続人(遺留分権利者)は、下記の者です(1028条)。
①配偶者
②子(またはその代襲相続人)
③直系尊属
なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。当然、その代襲相続人となった甥姪にも遺留分はありません。そのため、遺言書を作れば、兄弟姉妹に遺産を一切相続させないようにすることが可能です。
また遺留分は、法律上の相続人にのみ認められる権利ですので、内縁関係の配偶者や養子縁組をしていない配偶者の連れ子には認められませんし、相続欠格・廃除・相続放棄が認められた場合も、遺留分はなくなります。
3.遺留分の算定対象となる財産
遺留分の算定対象財産に組み入れられる財産については、下記の積極財産及び消極財産です。
≪積極財産≫
(ア)被相続人が相続開始時に有していた財産
(イ)遺贈や死因贈与された財産
(ウ)一定の要件を満たす贈与財産(下記の①~③)
≪消極財産≫
(あ)相続債務 (保証債務・連帯保証債務は原則含まれず)
※生命保険の死亡保険金は、誰が受取人であっても、原則として遺留分対象財産に加算されません。
【一定の要件を満たす贈与財産とは】
①相続開始1年以内の生前贈与財産
被相続人の死亡日から逆算して1年以内の贈与は、法定相続人以外の者に対する贈与であっても遺留分の対象財産に取り込まれます。
つまり、相続開始1年以内の駆け込み贈与については、誰に対する贈与でも全て遺留分の算定対象財産に含まれますので、注意が必要です。
なお、贈与契約が相続開始前の1年間に締結されたことが要件となりますので、1年以上前に締結された贈与契約が相続開始前の1年以内に履行された場合は、遺留分算定対象になりません。
②遺留分を侵害することを贈与者・受贈者が認識して贈与した財産
相続開始から1年以上前になされた生前贈与であっても、贈与する側(贈与者)及び贈与を受ける側(受贈者)の双方が、相続人の遺留分を侵害することを認識していながら贈与を実行した場合は、当該贈与財産は遺留分の対象に組み入れられます。
なお、「遺留分を侵害する認識」があればよく、損害を与えるという加害の意図や誰が遺留分権利者であるかを知っている必要はありません。
不相当な対価(安価)でなされた有償譲渡については、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行っていた場合、贈与とみなされ、無償で譲渡された財産相当(譲渡財産額から対価を差し引いた残額)が贈与分として加算されます。
③相続人に対する特定のの贈与財産(特別受益)
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益を言います。
特別受益者に該当するか否かは、生前贈与等がなされた時点において、贈与等を受けた者が推定相続人であったか否かによって判断します。
【第1030条】
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
4.遺留分の割合
遺留分権利者が取得できる遺産全体に対する割合を「遺留分割合」といい、下記の通りの割合になっています(1028条)。
以下の通り、遺留分割合を考慮すべき相続の形には、6パターンがありますが、分かりやすく言えば、下記⑤(相続人が父母のみ)の場合に限り3分の1となりますが、それ以外は、遺留分割合は「法定相続分の半分」だと理解してしまえば簡単です。
相続人のパターン
①配偶者と子・・・・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1(各法定相続分の半分)
※子が複数いれば、4分の1を頭数で均等割
②配偶者のみ・・・・・・・・2分の1(法定相続分の半分)
③子のみ・・・・・・・・・・2分の1(法定相続分の半分)
※子が複数いれば、4分の1を頭数で均等割
④配偶者と父母・・・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1(各法定相続分の半分)
※父母が複数(養父母も含め)いれば、6分の1を 頭数で均等割
⑤父母のみ・・・・・・・・・3分の1
※父母が複数(養父母も含め)いれば、6分の1を頭数で均等割
⑥配偶者と兄弟姉妹・・・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
【第1028条】 (遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
5.遺留分減殺請求の効果
遺言による指定を受けて、遺産を全くもらえない、または遺産を僅かしかもらえない相続人が、相続分の指定や遺贈・生前贈与(以下、「遺贈・贈与等」と言います。)によって侵害された自己の遺留分を主張(請求)する行為を「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせきゅう)」と言います。
遺留分減殺の意思表示は、遺留分を侵害している(遺贈・贈与等により多くの財産を取得している)相続人・受遺者・受贈者に対して行いますが、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者に対しても行うのが好ましいです(意思表示については、指定された方法はありませんが、通常は、配達記録付内容証明郵便で意思表示をします)。
意思表示が相手方に届いた時点で、法律上当然に遺留分減殺の効果を生じ、遺留分を侵害している部分に限り遺贈・生前贈与等の効果が失われ、遺留分権利者の所有に属することになります。そのため、理論上、不動産等が共有状態になることがしばしばあり得ます。
そこで実務上は、当事者間の話し合いを行い、遺留分相当の金銭を一括又は分割で支払う形で決着を図ることが多いです。もちろん、当事者間の話し合いが暗礁に乗り上げれば、遺産分割調停や訴訟手続きの中で解決図らざるを得ないケースもあります。あとは話し合いで、または場合によっては調停や訴訟によって、遺留分に見合う遺産を現実に取り戻すことになります。
なお、遺留分を侵害する内容の遺言であっても、当然に遺言全体が無効となるわけではありません。遺言の中の遺留分を侵害している部分が限定的に無効の取扱いを受けることになります。
従いまして、遺産の内容や遺留分減殺請求の内容によっては、遺言執行を中断して遺留分の早期解決を図ってから残りの遺言執行業務を遂行すべきケースもありますし、遺留分減殺請求がなされた後も、引き続き遺言内容の実現のための執行業務をそのまま遂行できる場合もありえます。後者の場合は、遺言執行業務完了後に当事者間で精算する作業が必要となります。
※ 割合的減殺の原則 (民法第1034条)
民法第1034条は、遺留分減殺請求の対象財産が複数存在する場合、原則として全ての財産からそれぞれの価額の割合に応じて減殺する旨を規定しています。
例えば、相続人が甲乙の2名で、遺言により全ての遺産を甲が相続することになったとしましょう。何も貰えない相続人乙は、遺留分割合として遺産の4分の1相当を遺留分侵害額として減殺請求できます。遺留分対象たる遺産が合計5,000万円(不動産が4,000万円、預金が1,000万円)だとしますと、遺留分減殺請求額は金1,250万円(5,000万円×1/4)相当ということになります。
この場合、遺留分減殺請求の効果として、各財産の比率(不動産4:預金1)に応じて、不動産から1,000万円相当を、預金口座から250万円を理論上乙が取得することになります。
つまり、当事者甲乙間で“価格弁償”の合意(不動産の持分を取得することを避けるために現金1,250万円を遺留分権利者に払う旨の合意)がなされなければ、理論上は、不動産の持分4分の1を乙が取得し、甲乙が不動産を共有することになります。
なお、減殺請求すべき財産が複数ある場合、遺留分権利者側で減殺の対象となる財産を選択できるかという論点がありますが、最近の学説では、減殺対象財産の選択を認めない学説が有力となっているようです。
6.遺留分減殺請求権の時効
遺留分権利者は、相続発生後、自分の遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に減殺請求を行わないと、その権利は時効によって消滅します。また、自分の遺留分が侵害されたと認識していなければ、1年の時効期間は進行しませんが、それでも相続開始時から10年経った場合も、時効により権利が消滅することになっています(民法第1042条)。
【第1042条】(減殺請求権の期間の制限)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
7.遺留分の生前放棄
遺留分の権利は、被相続人の生前に、つまり相続開始前に、家庭裁判所の許可を条件に放棄することができます。言い換えれば、将来の相続人(推定相続人)から遺留分を放棄する旨の念書や誓約書、覚書等を直筆等で作成してもらっても、法的な意味は全くありません。
遺留分を放棄する意思が明確でも、それだけでは家庭裁判所の許可を得ることはできません。「既に多額の生前贈与を受けている」・「生活に困っていないので将来遺産を受け取る意思は無い」・「生前中も相続後も今後一切の関わりを持ちたくない」などの事情や合理的な理由がある場合に、家庭裁判所が許可することになっています。
なお、共同相続人の1人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。つまり、遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分は増加しません。
また、遺留分を放棄しても相続放棄をしたことにはなりませんので、遺言が無ければ、通常通りの法定相続分を有することになり、その効果として必ず遺産分割協議には参加する必要があります(相続権を放棄したい場合は、被相続人の死後に改めて相続放棄の申立てをすることになります)。
つまり、遺留分の放棄は、『被相続人がどんな遺言を書こうとも一切の異議は申し立てません。』という効果を持つだけであり、遺言書の作成と合わせて行わなければ、何ら法的な意味はなさないことになるのです。
遺留分放棄申立て手続き
●申立人 遺留分を有する推定相続人
●申立ての時期 相続開始前
●管轄 被相続人の住所地の家庭裁判所
●手数料等 収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって異なります)
●必要書類 申立人・被相続人の戸籍謄本、財産目録
●家裁の審理
裁判所において、放棄意思の真意性・撤回の可能性、生前贈与などの有無、その他放棄する動機の合理性、申立人と被相続人との親疎・扶養関係などについて調査が行われ 審判が下されます。 審判により認容・却下のいずれの判断に対しても、不服申立ては出来ません。
なお、認容の審判が下りる基準は以下の通りです。
1. 放棄が本人の自由意思にもとづくものであるかどうか
2. 放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか
3. 代償性があるかどうか(たとえば放棄と引きかえに現金をもらうなど)
8.遺留分減殺請求に対する防御策
~請求対象財産の順序指定~
『遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。』(民法第1034条)との規定により、遺言者は、遺留分権利者が取得する遺産を予め指定しておくことができます。この指定があると、遺留分権利者は遺留分相当にみつるまで指定された財産から順番に主地区することになります。
例えば、遺言書の中で、減殺請求すべき遺産の順序を ①リゾートマンション ②ゴルフ会員権 ③上場株式 ④預金債権 ⑤自宅不動産としておくことにより、死守したい自宅不動産には遺留分減殺が及ばないようにブロックをかけることが可能です。
【第1034条】(遺贈の減殺の割合)
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。